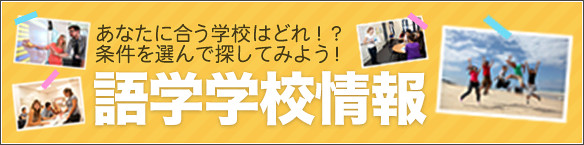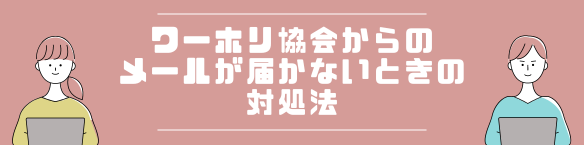ワーホリや留学に行きたいと思っている方に質問です!あなたがワーホリや留学をしたいと考える、その理由は何でしょうか?
以前ワーホリ協会が行ったアンケート調査では、7割以上の方が「語学力の向上」を渡航目的に選ばれました。
日本で就職する際でも、これからは第二言語の習得が必須といわれるようになってきています。ただ、日本で生活していては、どうしても日本語以外の言葉を使う機会がなく、、語学力を伸ばすことは難しいです。だからワーホリや留学を使って海外に渡航し、一気に語学力を身に着けよう!という考えですね。
この考え、実はとても合理的なんです!日本で1年間語学の勉強をするとしても、1日のうち勉強に割ける時間は多くて3~4時間でしょう。それ以外の時間は、どうやっても日本語を使うことになります。しかし、留学やワーホリを使えば、毎日就寝時間を除いたすべての時間、その国の言語に触れ続けることができるんです!8時間睡眠するとしても、毎日16時間以上になります!この差は大きい!なので、短期間で語学力を向上させたいならワーホリや留学に行くほうが良いと言えるでしょう。
ただし、「語学力の向上」を目的にするなら、もう少し具体的に「どれくらいの語学力を身につけたいのか」を考える必要があります。なぜなら、ある程度の目標を最初に作っておかないと、渡航中のモチベーション維持や、帰国後に直面する現実とのギャップに苦しむことになる可能性があるんです。
===
目標にできる語学力のレベルは、大きく6つに分けることができます。
1.「旅行で困らないくらいの語学力」
2.「日常生活ができるくらいの語学力」
3.「現地でアルバイト出来るくらいの語学力」
4.「帰国後の就職・転職に活かせる語学力」
5.「外資系などの仕事につけるくらいの語学力」
6.「海外就職できるくらいの語学力」
【1】や【2】のレベルであれば、半年程度海外で生活するだけでも身につけることができます。ただし、語学力で現地でのアルバイトや、帰国後の就職を有利に進めることはほぼできないと言えます。日常的に使う言葉だけでは語彙があまりに少なく、気が付かない間に相手に失礼な言い回しをしていることもあるので、まず仕事では使えません。
逆に【3】や【4】のレベルになると、ただ生活するだけではなかなか到達することができないでしょう。しっかりとした文法、十分な単語数、敬語などは、人から教えてもらわないと分からないものですし、友達はそういった間違いを指摘してくれません。なので、語学学校などに通う必要が出てきます。
【5】や【6】のレベルはビジネス・ネイティブレベルと呼ばれ、ただ英語が話せるだけでなく、敬語・マナー・単語量・かなり本気で勉強しなければ到達できません。しかし逆に言えば、1年くらい海外でしっかり語学の勉強をすることで、限りなくこのレベルに近づくことも可能です。
===
最後に知っておいていただきたいことなのですが、ワーホリや留学から帰ってきた方たちから、「もっと勉強すればよかった」という言葉を聞きます。
これは、「海外生活を通して語学力は身についたものの、出発前に自分が想定していたレベルには達しておらず、自分の自信につながっていないパターン」です。こうなると、せっかくのワーホリ・留学経験を「恥ずかしい」と思うようになり、経験を隠してしまったり、帰国後の就職に活かせなかったりするんです。
最初に語学力の目標を立てておくことで、このような事態も回避しやすくなります!まずは自分の語学目標を設定してみるように、心がけましょう!
【関連記事】