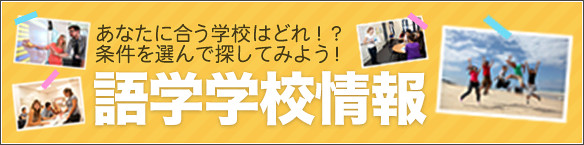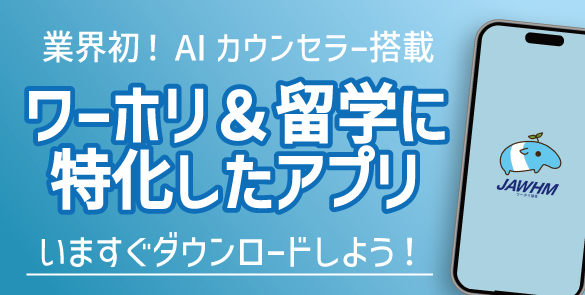日本の文化について書かれている英語コラムを、翻訳付きで紹介!
そして覚えておきたい英語表現も具体的に解説していきます。
この記事は【Part.4 & 5】です。【Part.1】はこちらから
Part.4 A PLACE FOR EVERYONE
誰でも楽しめる場所
While izakaya were often seen as a place for male businessmen up until the 1970s, izakaya to more feminine tastes in food and in drinks such as chuhai and wine are increasingly common, and many stores have worked on their interior to provide a place that anyone, women-only groups and families included, can enjoy.
1970年ごろまでの居酒屋はサラリーマンの場所というイメージが強かったのですが、チューハイやワインなど女性向けドリンクや食べ物の提供をはじめ、内装やインテリアにこだわるなど、女性だけのグループや家族でも楽しめるような空間を提供できるようにシフトし始めました。
※「up until ~」… ~までは
In the 1980s, izakaya chain stores started popping up, and they came to be known as places with a good range of low-cost food and drink, and a venue where large groups can gather informally without having to worry about a bit of boisterousness. This accessible image has made izakaya a popular place for students, businesspeople, and friends to hold simple gatherings. Those out by themselves are more than welcome, too.
1980年代になると数多くの居酒屋チェーン店が出現し、「安く飲み食いでき、大勢がカジュアルに集まって騒げる場所として知られるようになりました。居酒屋はより身近な、学生や会社員、友達で集まれる場所になったのです。それは、歓迎されるべきものでした。
※「boisterousness」… にぎやか、陽気、喜々
※「accessible」… 近づきやすい、利用しやすい
Part.5 IZAKAYA ETIQUETTE
居酒屋のエチケット
Some izakaya also offer the option of smoking areas. While the number of nonsmoking stores has risen in recent years, some permit smoking. For those looking to enjoy their time without worrying about smoke, nonsmoking seats are also available.
居酒屋によっては喫煙席が用意されています。近年では禁煙席も増えてきましたが、まだ喫煙は許されています。煙を気にせず楽しみたい人は、禁煙席を使いましょう。
※「permit」 … 許可
Some izakaya have seating areas where you must take off your shoes at the door, so it is a good idea to be wearing clean socks! Finally, other locations for a good drink in Japan include snack bars, cabarets, and clubs, the last two offering a uniquely Japanese style where female staff members serve drinks and enjoy a chat with the clientele.
居酒屋によってはお店に入るときに靴を脱がないといけないので、きれいな靴下を履いておきましょう!最後に、居酒屋以外にもスナックバー、キャバレー、クラブなどがあり、これらのお店では女性スタッフがお酌をしてくれる、日本ならではの楽しみ方があります。
※「it is a good idea to ~」… ~するのが良い
面白かったですか?まだ全文を確認してない方は、是非【Part.1】から読んでみてくださいね!
≫≫【Part.1】から読んでみる!
日本の事、英語で伝えられる?

【コラム出典元】
[ jStyle ] 【Food】Genuine Izakaya Experience(20/05/2016)
https://j-style.com.au/category/food/sake/